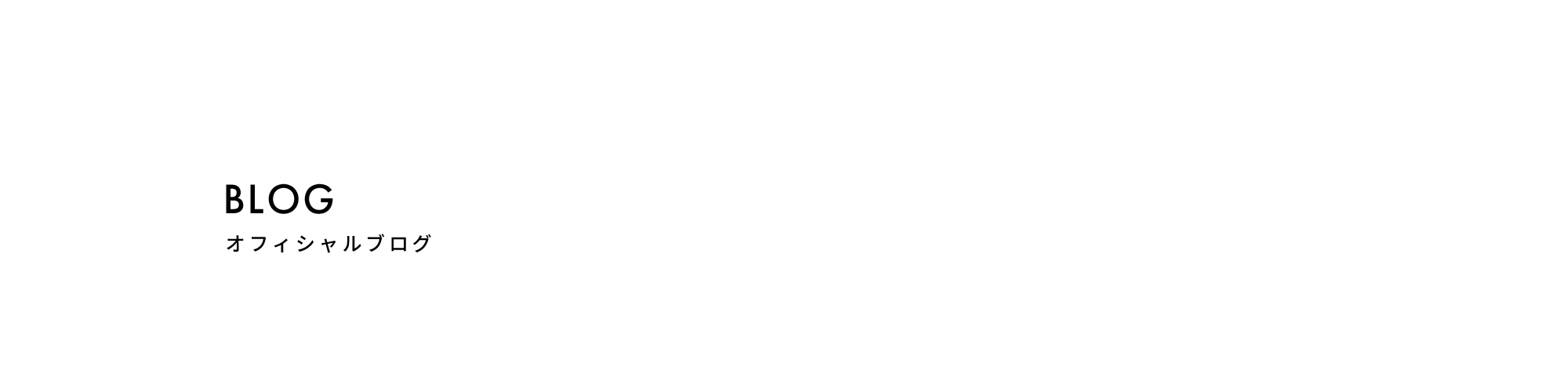
月別アーカイブ: 2025年4月
第3回左官工事雑学講座
皆さんこんにちは!
株式会社ヤマダ、更新担当の中西です。
第3回左官工事雑学講座
テーマ:左官工事で使われる道具と材料
前回は左官工事の具体的な流れや職人が大切にしているポイントについて解説しました。
今回は、左官工事に欠かせない道具や材料を詳しくご紹介します。
どんな道具や材料を使うかによって、仕上がりの質や作業効率も変わってくるんですよ!
1. 左官工事の主な道具
◎ コテ(こて)
-
最も代表的な道具がコテです。塗りつけや仕上げの際に使用し、仕上がりの表情を左右する重要な道具です。
-
材質や形状がさまざまで、ステンレスコテはサビに強く扱いやすい一方、木コテはナチュラルな質感を出したいときに使うなど、用途に応じて使い分けます。
◎ コテ板・練板(ねりいた)
-
コテ板とは、左官材を一時的に乗せておくための板です。
-
練板と呼ばれる大きい板もあり、材料を練り混ぜたり、複数の職人が同時に材料を取ったりする際に重宝します。
◎ 水平器・下げ振り
-
壁や床が平行・垂直になっているかを正確に測るための道具。
-
水平器は泡の入ったカプセルで水準を見極め、下げ振りは糸の先に重りをつけて垂直を確認します。
◎ バケツ・桶(おけ)
-
材料の練りや混合、水をはかる際に使います。大きさや形状が作業内容によって変わることも。
-
プラスチック製から金属製まで多種多様。持ち運びのしやすさも考慮して選びます。
◎ へらやブラシ類
-
細部の仕上げや、余分な材料の除去などに用いる道具。
-
コテでは届かない部分の調整や、模様付けの際に活躍します。
2. 左官工事で使われる主な材料
◎ モルタル
-
セメント + 砂 + 水を混ぜたもの。強度があり、壁や床の下地材として多用されます。
-
仕上げ用に微粒の砂を使ったものや、防水性を高める添加剤を加えたものなど、用途に合わせた種類が豊富。
◎ 漆喰(しっくい)
-
消石灰 + 水 + 砂などを混ぜ合わせた自然素材。
-
調湿効果や防カビ効果が期待でき、和風建築や自然派志向の住宅で人気があります。
◎ 珪藻土(けいそうど)
-
海や湖の底に堆積した珪藻(けいそう)の化石からなる土。
-
漆喰同様に調湿性能が高く、室内壁の仕上げ材として利用されることが多いです。
◎ 砂・骨材
-
モルタルやコンクリートに混ぜる砂や小石。
-
粗さや粒度が変わると仕上がりの質感や強度が変わるため、目的に応じて粒度を選びます。
◎ 防水材や添加剤
-
バスルームや外壁など、水気の多い場所での施工には、防水性や耐久性をアップさせる防水材・添加剤を混ぜ込むことも。
-
ひび割れを抑える、早期乾燥させるなど、機能性を高める助けになります。
3. 道具と材料が組み合わさる施工ポイント
-
練りの工程でのこだわり
-
材料を適切な割合で混ぜることが、作業のしやすさや最終的な仕上がりに直結。
-
職人の経験が大きく活きる部分で、湿度や気温を見ながら水の加減を微調整することも。
-
-
コテ使いの妙
-
コテの角度や圧力、手の動かし方ひとつで、表面の平滑度や模様の入り方が変わります。
-
「コテ波」と呼ばれる模様や、彫刻のようなデザインを施す場合もあり、職人のセンスや技術が光る場面です。
-
-
道具のメンテナンス
-
コテや練板は、使用後すぐに水洗いし、材料が固まって付着しないようにするのが基本。
-
錆びや汚れを防ぎ、常に良好なコンディションを保つことで、仕上がりの品質と効率がアップします。
-
4. 種類豊富な仕上げテクニック
-
砂壁仕上げ: 砂粒の粒度を活かし、ザラリとした質感が特徴。和風の住宅や旅館などでよく見られます。
-
鏝(こて)押さえ仕上げ: コテを何度も押さえることで、艶やかな平滑面を作り出す仕上げ。漆喰やモルタルの上塗りに最適。
-
スタンプ仕上げ: モルタルが半乾きの状態で模様のついた型を押し当て、ブロックや石のような見た目を再現。庭のアプローチなどに使われます。
-
刷毛(はけ)引き仕上げ: ブラシやハケで表面に筋を入れることで、滑り止め機能を持たせたり、独特の模様を作る技法。
まとめ
-
道具: コテやコテ板、ブラシなど、多種多様な道具を使い分けることで美しい仕上がりを実現
-
材料: モルタル・漆喰・珪藻土など、用途やデザインに合わせて最適なものを選ぶ
-
練りやコテ使い: 職人の経験と技術が大きく影響する工程。手の感覚が仕上がりを左右
-
仕上げテクニック: 砂壁や鏝押さえ、スタンプなど、表情豊かな仕上がりを作り出せる
左官工事の道具や材料は一見地味な印象かもしれませんが、
これらを使いこなすことで、驚くほど多彩な表情の壁や床が生まれます。
家や建物に温もりや味わいを与えるのが左官の魅力です。
次に左官工事を見る機会があれば、ぜひ道具や材料にも注目してみてください!
以上、第3回左官工事雑学講座でした!
次回は、「左官仕上げの種類とインテリア活用術」をテーマに、さらに深く仕上げテクニックのバリエーションを掘り下げていきます。
どうぞお楽しみに!
株式会社ヤマダでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用で最も大切にしているのは「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。
皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()


